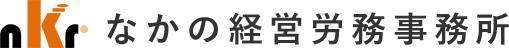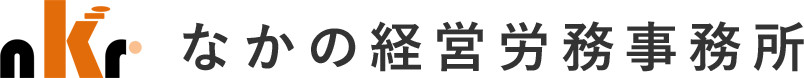厚生労働省より「令和6年度雇用均等基本調査」結果が公表され、その調査結果の中で男性の育児休業取得率が大幅に上昇していることが明らかになりました。
具体的には、2022年 10 月1日から2023年9月 30 日までの1年間に配偶者が出産した男性のうち、2024年 10 月1日までに育児休業(産後パパ育休を含む。)を開始した者(育児休業の申出をしている者を含む。)の割合は 40.5%と、前回調査(2023年度 30.1%)より 10.4 ポイント上昇しています。
2024年8月にご紹介した次の「若年層における育児休業等取得に対する意識調査」の結果においても、若年男性の84.3%が育児休業を取得したいと回答していました。
若年男性の84.3%が育児休業を取得したいと回答しました(なかの経営労務事務所)
毎年社会人になる若年者は少子化の影響により減少傾向にあり、その若年者は企業間の奪い合いによって賃金が上昇しています。
特に若年の男性社員の雇用を確保したいのであれば、賃金だけでなくたとえ男性であっても育児休業を取得しやすい職場環境を整備することは事業主としての必須の責務でしょう。
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
【PDF】「令和6年度雇用均等基本調査」結果を公表します(厚生労働省)
令和6年度雇用均等基本調査(厚生労働省)
【昨年の記事】令和5年度の男性育児休業取得率は30.1%です(令和5年度雇用均等基本調査より)(なかの経営労務事務)
具体的には、2022年 10 月1日から2023年9月 30 日までの1年間に配偶者が出産した男性のうち、2024年 10 月1日までに育児休業(産後パパ育休を含む。)を開始した者(育児休業の申出をしている者を含む。)の割合は 40.5%と、前回調査(2023年度 30.1%)より 10.4 ポイント上昇しています。
- ※女性はここ20年の間およそ80%で推移していますが、男性はここ2年間で急増しています。
2024年8月にご紹介した次の「若年層における育児休業等取得に対する意識調査」の結果においても、若年男性の84.3%が育児休業を取得したいと回答していました。
若年男性の84.3%が育児休業を取得したいと回答しました(なかの経営労務事務所)
毎年社会人になる若年者は少子化の影響により減少傾向にあり、その若年者は企業間の奪い合いによって賃金が上昇しています。
特に若年の男性社員の雇用を確保したいのであれば、賃金だけでなくたとえ男性であっても育児休業を取得しやすい職場環境を整備することは事業主としての必須の責務でしょう。
詳細は次のURLよりご確認頂けます。
【PDF】「令和6年度雇用均等基本調査」結果を公表します(厚生労働省)
令和6年度雇用均等基本調査(厚生労働省)
【昨年の記事】令和5年度の男性育児休業取得率は30.1%です(令和5年度雇用均等基本調査より)(なかの経営労務事務)

システム関連に強く、人事総務部門のトータルアウトソーシングのプランニングおよび受託を得意とする。さらに、人事労務系のコンサルティングに力を入れており、人事制度構築コンサルティングのほか、M&Aコンサルティング等、企業の経営企画部門、人事労務部門の双方の支援をしている。