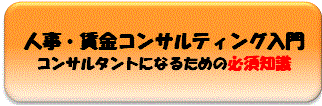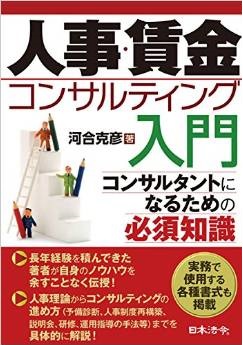人事・賃金コンサルティング入門 |
||||||||||||||||||
本書の内容
筆者は35年近く人事コンサルタントをやってきた。その体験やノウハウを次の世代に伝えることが古稀を迎えようとしている筆者の役割かなと思って本書を書いた。 「人事コンサルタントを目指す人に」、「提案する人事システムの理論」、「コンサルティングの進め方(予備診断、人事制度再構築、説明会、研修、運用指導の手法まで)」がその内容になっており、いわば筆者のコンサルティングの集大成という内容になっている。 人事コンサルタントに必要な知識は下図に示すように「経営に関する基本的知識」「人事管理に関する基本的知識」「コンピュータに関する基本的知識」と言った基本的知識をベースに「人事理論に関する知識」「人事コンサルティングの進め方に関する知識」が必要である。 「経営に関する基本的知識」「人事管理に関する基本的知識」と言った基本的知識は、中小企業診断士、社会保険労務士の試験科目になっており、そこでしっかり勉強すればよく、本書はその基本的知識を踏まえた上で「人事理論に関する知識」「人事コンサルティングの進め方に関する知識」を修得するための本と位置づけている。 それではこれらの知識をマスターすればコンサルタントになれるかというと、それは難しい。コンサルティングというのは、こうした知識をベースに実際の会社で経験を積むことが必要であるからである。その場合、よい師を見つけ、その師について学ぶことが重要ではないかと思う。 労政時報の人事ポータル jin-Jour BOOK REVIEW 『人事・賃金コンサルティング入門』 人事コンサルタントになるには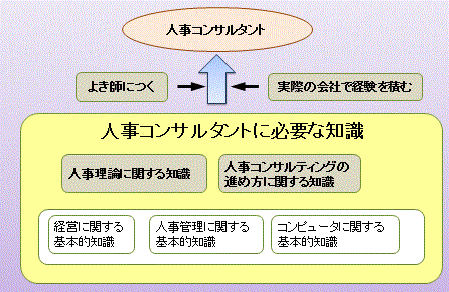 本書の目次はじめに
LessonⅠ 人事コンサルタントを目指す人に
1 人事コンサルティングの領域は広い
(1) 人事コンサルティングの中核をなすもの (2) 人事制度構築の川上 (3) 人事制度構築の川下 (4) 人事コンサルティング以外の活動 2 私がコンサルタントになった経緯 3 人事コンサルタントに必要な知識 4 開業社労士が人事コンサルティングの知識・ノウハウを身につけると 事務所を格段に強化できる (1) うまくいっていないケース~Aさんの場合 (2) うまくいっているケース~Bさんの場合 (3) うまくいっているケースの分析 5 人事コンサルタントを目指す人が留意すること (1) 一気通貫した理論性をもった人事制度を学ぶこと ① 学ぶべき人事制度は人事制度全部であること ② 学ぶべき人事制度は1つの理念に貫かれており、かつ理論的であること (2) よき師のもとでコンサルティングの実践を積むこと (3) ノウハウとして蓄積すること (4) 「人事」という狭い視点から見るのではなく広い視点で見ること (5) コンサルティングが好きになること LessonⅡ 提案する人事システムの理論
1 トライアングル人事システムのコンセプト
2 役割・能力・成果を明確にする (1) ステージ制度 (2) 役割能力要件表 (3) 役割能力要件表読み方 ① 「期待される役割」の読み方 ② 「必要とされる知識技能」の読み方 (4) 役割能力要件表と各種評価との関係 (5) バランスの取れた評価制度 (6) 役割能力要件は人事制度の核 (7) 成果とは (8) 管理職の成果 ① 部門業績責任者 ② 部門活性化推進者 ③ 管理職の成果をどう捉えるか (9) 一般社員の成果 3 評価システム (1) 業績評価 ① 得意とするところで把握 ② 業績評価項目とウエイト ③ 役割期待評価 ④ 加点・減点 ⑤ 業績評価得点の計算 ⑥ 評価期間 ⑦ 一次評価・二次評価 (2) 個人目標 ① 目標管理の強み ② 目標管理の強みを生かす ③ 個人目標の評価 ④ 個人目標の評価得点の計算 (3) 部門業績 ① 部門業績とは ② 部門業績評価制度構築のステップ ③ 部門業績評価項目・ウエイト表、部門業績の把握方法、評価基準 ④ 部門業績評価得点の計算 (4) チャレンジ加点 ① プロジェクト加点 ② パーソナル加点 ③ エクセレント加点 ④ 評価委員会 (5) 能力評価 ① 役割能力要件と能力評価の関係 ② 職務の評価 ③ 知識技能力評価 ④ 昇格可能性の評価 4 処遇システム (1) 昇格 ① 昇格基準1 ―― 業績評価 ② 昇格基準2 ―― 能力評価 ③ 昇格基準3 ―― 審査 ④ 降格 (2) 賃金構成 ① 役割給 ② ステージ手当 ③ 職位手当 ④ 賃金組替 (3) 昇給 ① 賃金表によらない昇給計算の仕組み ② 若年層の昇給 ③ 昇給原資の配分 ④ 昇給計算の実際 (4) 賞与 ① 賞与計算の仕組み ② 賞与計算の実際 ③ 賞与計算の実際のまとめ (5) 退職金 5 トライアングル人事システムの全体像 LessonⅢ 人事コンサルティングのプロセス
1 人事コンサルティングの概観
2 営業 (1) 現在のつながり (2) 紹介・口コミ (3) 人脈 (4) セミナー (5) 著作 (6) 営業スタッフ 3 コンサルティングニーズの聴き取りとコンサルティング構想 (1) コンサルティングニーズ聴き取り (2) コンサルティング構想 4 企画書 (1) 表紙 (2) 背景 (3) 目的 (4) 人事制度の再構築・導入・定着化のスケジュール (5) コンサルティング・ステップ (6) 内容 (7) スケジュール (8) 費用 (9) 担当者 5 契約・コンサルティングの実施・請求 (1) 契約 (2) コンサルティングの実施 ① 予備診断 ② 人事制度の再構築 ③ 説明会・研修・運用指導・ソフト開発 (3) 請求 LessonⅣ 予備診断
1 事前に提供してもらう資料
2 インタビューのやり方、留意点 (1) インタビューの人数 (2) インタビューの時間 (3) インタビューの場所 (4) インタビューの人選 (5) インタビューのスケジュール表 (6) インタビューの案内状 (7) インタビューの時に気をつけること ① インタビューの最初に話すこと ② 話の順序 ③ 聴く時に留意すること 3 インタビューのまとめ方 4 予備診断報告書 (1) 調査概要 (2) 経営課題 (3) 課題解決の施策 (4) 新人事制度の基本構想 (5) 現行人事制度の分析 ① 社員構成 ② 等級と職位の関係 ③ 昇格 ④ 人事考課 ⑤ 教育研修制度 ⑥ 賃金制度 ⑦ 昇給 ⑧ 賞与 ⑨ 賃金水準 ⑩ モデル別賃金・年収の推計 ⑪ 退職金 (6) 財務分析 LessonⅤ 人事制度再構築
1 プロジェクトチームを組成して行うか、こぢんまり行うか
(1) 会社の実態に合った人事制度が再構築できる (2) 役割能力要件表の作成がスムーズにできる (3) 再構築した人事制度の運用がスムーズにできる (4) 労働組合の理解が得やすい 2 プロジェクトチームを組成して行う場合 (1) プロジェクトの組成 ① プロジェクトの人数は何人がよいか ② プロジェクトの時間はどうするか ③ プロジェクトチームのメンバーをどう選ぶか ④ 経営トップをプロジェクトチームのメンバーに入れるかどうか ⑤ プロジェクトチームを公式なものとする (2) プロジェクトのスケジュール (3) プロジェクトの具体的進め方・留意事項 ① 第1回プロジェクトまでに行うこと ② 第1回プロジェクト ③ 第2回プロジェクトまでに行うこと ④ 第2回プロジェクト ⑤ 第3回プロジェクトまでに行うこと ⑥ 第3回プロジェクト ⑦ 第4回プロジェクトまでに行うこと ⑧ 第4回プロジェクト ⑨ 第5回プロジェクトまでに行うこと ⑩ 第5回プロジェクト ⑪ 第6回プロジェクトまでに行うこと ⑫ 第6回プロジェクト ⑬ 第7回プロジェクトまでに行うこと ⑭ 第7回プロジェクト ⑮ 第8回プロジェクトまでに行うこと ⑯ 第8回プロジェクト ⑰ 第9回プロジェクトまでに行うこと ⑱ 第9回プロジェクト ⑲ 第10回プロジェクトまでに行うこと ⑳ 第10回プロジェクト 21 第11回プロジェクトまでに行うこと 22 第11回プロジェクト 23 第12回プロジェクトまでに行うこと 24 第12回プロジェクト 3 こぢんまり行う場合 4 シミュレーションと新人事制度諸規程 (1) シミュレーション (2) 新人事制度諸規程 5 新人事制度解説書 LessonⅥ 役割能力要件表の構築
1 役割能力要件表構築のアウトライン
(1) 役割能力要件表構築の基本的スタンス ① 完璧を狙わない ② 職務調査は必ずしも必要ではない ③ 実際の運用が大切 (2) 構築推進組織 (3) 構築のステップ 2 STEP1 ステージのイメージを固める (1) ステージの段階をどのくらいにするか (2) 職掌の設定 3 STEP2 マトリックス表で全職掌共通のものを作る (1) 全職掌共通・期待される役割マトリックス表 (2) 全職掌共通・必要とされる知識技能マトリックス表 (3) 全職掌共通・必要とされる知識技能の具体的内容 4 STEP3 マトリックス表で職掌固有のものを作る 5 STEP4 マトリックス表で監督職、管理職、専門職のものを作る (1) 監督職 (2) 管理職 (3) 専門職 6 STEP5 細部を検討・調整する (1) 横の関係を見る (2) 業績評価項目との整合性をとる (3) 用語を統一する (4) その他の検討、調整 7 STEP6 役割能力要件表にコピーして完成させる (1) 役割能力要件表を一覧化する (2) 監督職、管理職、専門職の役割能力要件表 (3) 役割能力要件表の実際例 LessonⅦ 説明会・研修・運用指導・ソフト開発
1 人事制度は運用がポイント
2 新人事制度説明会 3 管理職向け研修 (1) 部門重点施策設定研修 (2) 評価者基礎研修 (3) 評価者実践研修―1 (4) 能力評価研修 (5) 個人目標設定指導研修 (6) 評価評価者実践研修―2 4 一般社員向け研修 (1) 個人目標設定研修 (2) 被評価者研修 (3) 能力評価研修 (4) 個人目標実践研修 5 運用指導 6 運用ソフト (1) 運用ソフトの開発をどうするか (2) 運用ソフトの概念図 ① 業績評価 ② 能力評価 ③ 社員マスター ④ 各種設定テーブル ⑤ 昇給計算 ⑥ 賞与計算 ⑦ その他 (3) ワークシート出力ソフトの概念図 巻末資料 別表・別紙・索引・参考文献・著者紹介
|
||||||||||||||||||