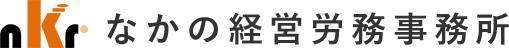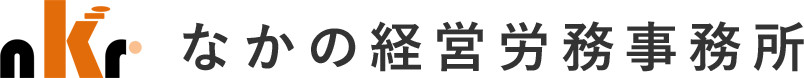同一労働同一賃金の法律について解説
―法令を正しく理解するために―
なかの経営労務事務所では、人事評価制度、賃金制度のコンサルティングを実施していますが、人事評価制度、賃金制度を整備するにあたっては企業規模を問わず「同一労働同一賃金(正規と非正規の不合理な待遇差禁止)」の内容を正しく理解した上で取り組む必要があることを痛感しています。
目次
同一労働同一賃金の法令の理解に向けて(本記事の目的)
我が国における同一労働同一賃金とは、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)との間の不合理な待遇差の解消を目指すものであり、具体的には「均等待遇」と「均衡待遇」の2つの定めがあります。
同一労働同一賃金とは政府が掲げるスローガンのようなものであり、単に同一の労働をしていれば同一の賃金を支払わなければならない、といった類のものでは無いのです。
筆者は、我が国における同一労働同一賃金(以下、単に「同一労働同一賃金」といいます)を理解する為には「法令の理解」、「判例の理解」の二つの理解が必要であると考えています。
そこで本記事ではまず「法令の理解」を手助けすべく、同一労働同一賃金に関する法改正経緯を紐解くことで、同一労働同一賃金の理解を深めることを目的として作成しました。
同一労働同一賃金について定めている法律条文
同一労働同一賃金について定めた法律条文は現時点(2025年4月時点)においてパートタイム・有期雇用労働法第8条、第9条、労働者派遣法第30条の3及び第30条の4です。
(不合理な待遇の禁止)
第8条 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。
(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止)
第9条 事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(第十一条第一項において「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」という。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの(次条及び同項において「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」という。)については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。
※本記事ではパートタイム、有期雇用労働者に絞った解説をする趣旨から労働者派遣法に関する解説は割愛します。
均等待遇・均衡待遇とは何か
我が国における同一労働同一賃金を理解する上で「均等待遇」、「均衡待遇」の理解は欠かせません。
「均等待遇」とはなにか?
「均等待遇」とは、下記①及び②が同じ場合は差別的取り扱いを禁止するものです。- ①業務の内容及び責任の程度(以下、職務内容)
- ②職務内容・配置の変更範囲
現行法では、パートタイム・有期雇用労働法第9条に定められています。
「均衡待遇」とはなにか?
「均衡待遇」とは、待遇差が存在する場合は以下の①及び②の違い並びに③を考慮して、不合理な待遇差を禁止するものです(言い換えれば不合理と認められる待遇差以外の待遇差は合法となります)。
- ①職務内容
- ②職務内容・配置の変更範囲
- ③その他の事情
現行法では、パートタイム・有期雇用労働法第8条に定められています。
【PDF】雇用形態に関わらない公正な待遇の確保(厚生労働省) 【PDF】均衡・均等待遇(同一労働・同一賃金)(東京都)
現行法に改正されることとなった経緯
「均等待遇」、「均衡待遇」を正しく理解する為に、まずは現行法が施行される前の法律及び現行法に改正されることとなった経緯を見ていきましょう。
・1993年(平成5年)12月1日 パートタイム労働法が施行
女性の労働市場参加、高齢労働者の増加、サービス経済化などによってパート労働者が増加し、雇用形態の多様化が進み始め、これを労働法制に適応させるためにパートタイム労働法が施行されました。しかしその内容は全て努力義務であり実効性に乏しいものでした。なお、この時点では「均等待遇」、「均衡待遇」ルールを定めた規定は存在しません。
・2008年(平成20年)4月1日 改正パートタイム労働法が施行
1990年代後半から非正規雇用労働者が大幅に増加するとともに、1996年の丸子警報器事件にみられるように、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との処遇格差問題への関心が高まったことを受け、2008年にパートタイム労働法が全面改正されるに至りました。
【Link】第9条のポイント(厚生労働省)
また、「すべての待遇」についてパートタイム労働者であることを理由に差別的に取り扱うことが禁止される「均等待遇」ルールが改正パートタイム労働法旧第8条に義務規定として定められました。
具体的には①職務の内容が当該事業所の通常の労働者と同一の短時間労働者であって、②期間の定めのない労働契約を締結しており、③人材活用の仕組みや運用などが全雇用期間を通じて同じ(職務の内容および配置の変更の範囲が通常の労働者と同一と見込まれるもの)、については、賃金、教育訓練、福利厚生施設その他の待遇について差別的取り扱いをしてはならないと規定されました。
【Link】第8条のポイント(厚生労働省) 【Link】パートタイム労働法のポイント(厚生労働省)
・2013年4月1日(平成25年)4月1日 改正労働契約法が施行
労働政策審議会労働条件分科会2011年12月29日の建議に基づき、パートタイム労働法に先行して労働契約法が改正され、改正労働契約法旧第20条に無期契約労働者と有期契約労働者との不合理な労働条件を禁止する「均衡待遇」の義務規定が新設されました。
(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)
旧第20条 有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。
労働契約法旧第20条に規定された「均衡待遇」は、職務の内容等が同一でなくともその処遇格差が不合理に大きすぎて納得できないという問題を解消する役割を担いました。
労働契約法旧第20条は日本の雇用システムにおける非正規問題に即した政策的是正規制として「不合理な待遇差の禁止」という日本独自の「均衡待遇」の規範を法律に規定した意義は大変大きかったと筆者は考えます。
【PDF】有期労働契約の在り方について(建議)(厚生労働省)
→P4「4 期間の定めを理由とする不合理な処遇の解消」をご覧ください
・2015年(平成27年)4月1日 改正パートタイム労働法が施行
2008年施行のパートタイム労働法旧第8条に規定された「均等待遇」のルールの①から③の3要素を全て満たすパート労働者の比率はわずか1.3%にすぎませんでした。その問題を解消すべく様々な検討がなされた結果、パートタイム労働法を改正し「②期間の定めのない労働契約を締結しており」を削除して、残りの2要素が通常の労働者と同一であるパート労働者についての差別的取り扱いの禁止を定めた「均等待遇」が改パートタイム労働法旧第9条に義務規定として存続(旧第8条を改正法の旧第9条に移行)することになりました。
【Link】パートタイム労働法が変わります(平成27年4月1日施行)(三重労働局) 上記より、現行法が施行される直前は、労働契約法旧第20条に無期契約労働者と有期契約労働者との「均衡待遇」、パートタイム労働法旧第8条にパート労働者と通常労働者の「均衡待遇」、パートタイム労働法旧第9条にパート労働者と通常労働者の「均等待遇」のルールが規定されていたことになります。
・2020年(令和2年)4月1日 パートタイム・有期雇用労働法が施行
※中小企業は1年後の2021年(令和3年)平成4月1日より施行
現行法(パートタイム・有期雇用労働法)への改正が議論された当時においても、非正規雇用労働者は雇用者の約4割を占め減少する見通しは立っておらず約4割を占める非正規雇用労働者は職場で不可欠な存在となっていました。しかし、当時の法制度の下では正規雇用との間に賃金・一時金だけでなく、休暇や福利厚生などの格差が依然としてあるにも関わらず、不合理な格差の解消は期待できない状況であり待ったなしの課題になっていました。
【PDF】働き方改革実行計画(首相官邸)
4年間のアベノミクスは大きな成果を生み出した。(略)
日本経済再生に向けて、最大のチャレンジは働き方改革である。(略)「正規」、「非正規」という2つの働き方の不合理な処遇の差は、正当な処遇がなされていないという気持ちを「非正規」労働者に起こさせ、頑張ろうという意欲をなくす。これに対し、正規と非正規の理由なき格差を埋めていけば、自分の能力を評価されていると納得感が生じる。納得感は労働者が働くモチベーションを誘引するインセンティブとして重要であり、それによって労働生産性が向上していく。(略)働き方改革こそが、労働生産性を改善するための最良の手段である。生産性向上の成果を働く人に分配することで、賃金の上昇、需要の拡大を通じた成長を図る「成長と分配の好循環」が構築される。
他方、個人消費や設備投資といった民需は、持ち直しつつあるものの、足踏みがみられる。我が国の経済成長の 隘路(あいろ)の根本には、少子高齢化、生産年齢人口減少すなわち人口問題という構造的な問題に加え、イノベーションの欠如による生産性向上の低迷、革新的技術への投資不足がある。日本経済の再生を実現するためには、投資やイノベーションの促進を通じた付加価値生産性の向上と、労働参加率の向上を図る必要がある。そのためには、誰もが生きがいを持って、その能力を最大限発揮できる社会を創ることが必要である。一億総活躍の明るい未来を切り拓くことができれば、少子高齢化に伴う様々な課題も克服可能となる。
- ・同一労働同一賃金の導入は、仕事ぶりや能力が適正に評価され、意欲をもって働けるよう、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すもの。
- ・雇用形態に関わらない均等・均衡待遇の確保に向けて、政府のガイドライン案を策定。本ガイドライン案は、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差が不合理なものでないのかを示したもの。
- ・今後、本ガイドライン案を基に、法改正の立案作業を進める。ガイドライン案については、関係者の意見や改正法案についての国会審議を踏まえて、最終的に確定し、改正法の施行日に施行することとする。
- ・対象は、基本給、昇給、ボーナス、各種手当といった賃金にとどまらず、教育訓練や福利厚生もカバー。
- ・原則となる考え方を示すとともに、中小企業の方にもわかりやすいよう、典型的な事例として整理できるものについては、問題とならない例、問題となる例として、事例も多く取り入れている。
- ・ガイドラインに記載していない待遇を含め、不合理な待遇差の是正を求める労働者が裁判で争えるよう、その根拠となる法律を整備。
- ・本ガイドラインは、同一の企業・団体における、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を是正することを目的としているため、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間に実際に待遇差が存在する場合に参照されることを目的としている。このため、そもそも客観的にみて待遇差が存在しない場合については、本ガイドラインは対象としていない。
→ガイドライン案の構造についてはP5をご覧ください
同一労働同一賃金ガイドラインは次のURLよりご確認頂けます。
「本ガイドライン案を基に、法改正の立案作業を進める」とされているとおり、同一労働同一賃金ガイドラインと一体となって立案された改正法の骨子は次のとおりです。
-
1. 不合理な待遇差を解消するための規定の整備(パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法)
短時間・有期雇用労働者に関する同一企業内における正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止に関し、個々の待遇ごとに、当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化。併せて有期雇用労働者の均等待遇規定を整備。
派遣労働者について、次のいずれかを確保することを義務化。- ①派遣先の労働者との均等・均衡待遇
- ②一定の要件※を満たす労使協定による待遇
(※)同種業務の一般の労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金であること等
また、これらの事項に関するガイドラインの根拠規定を整備。
短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明を義務化。
→P1 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保をご覧ください。
【Link】第146回労働政策審議会労働条件分科会(厚生労働省) 【PDF】雇用形態に関わらない公正な待遇の確保(厚生労働省)
こうして立案されたパートタイム・有期雇用労働法案(働き方改革関連法案の一部)が2018年6月29日に成立し、パートタイム・有期雇用労働法は2020年4月1日(中小企業は1年遅れの2021年4月1日)より施行されることとなりました。
まとめ(現行法における「同一労働同一賃金」とは何か)
現行法(パートタイム・有期雇用労働法)における「均衡待遇」、「均等待遇」は、パートタイマーと有期雇用労働者に適用される法律を統合(パートタイム労働法からパートタイム・有期雇用労働法に改称)しつつ、長澤運輸事件最高裁判決(H30.6.1)、ハマキョウレックス事件最高裁判決(H30.6.1)を踏まえて条文の明確化を図ったものといえるでしょう。
(不合理な待遇の禁止)
第8条 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。
(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止)
第9条 事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(第十一条第一項において「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」という。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの(次条及び同項において「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」という。)については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。
パートタイム・有期雇用労働法第8条の変更点については「労働法第十三版 菅野和夫 山川隆一著(弘文堂)」P857に端的かつ分かりやすく解説されていますので該当箇所を抜粋します。
パートタイム・有期雇用労働法第8条(「短時間・有期雇用労働法8条」と記載されていたものを筆者が本記事における表現の整合性をとるために修正)は、旧労働契約法第20条を修正して(ア)「期間があることにより」を削除し、(イ)「待遇のそれぞれについて」判断することを明示し、(ウ)「職務の内容」、「職務の内容及び配置の変更の範囲」、「その他の事情」との判定要素に「のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるもの」との文言を付している。これら修正のうち、(ア)は不要の文言を削除しただけであり、(イ)は長澤運輸事件最判における判旨で先取りして述べられており、(ウ)はハマキョウレックス事件最判ですでに具体的に実践されている
さらにパートタイム・有期雇用労働法では「通常の労働者」との待遇差の内容や理由などに関する使用者の説明義務を強化することの規定、行政による事業主への助言・指導や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備等の規定も設けられ、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保について実効性を確保した法律と言えるでしょう。

システム関連に強く、人事総務部門のトータルアウトソーシングのプランニングおよび受託を得意とする。さらに、人事労務系のコンサルティングに力を入れており、人事制度構築コンサルティングのほか、M&Aコンサルティング等、企業の経営企画部門、人事労務部門の双方の支援をしている。